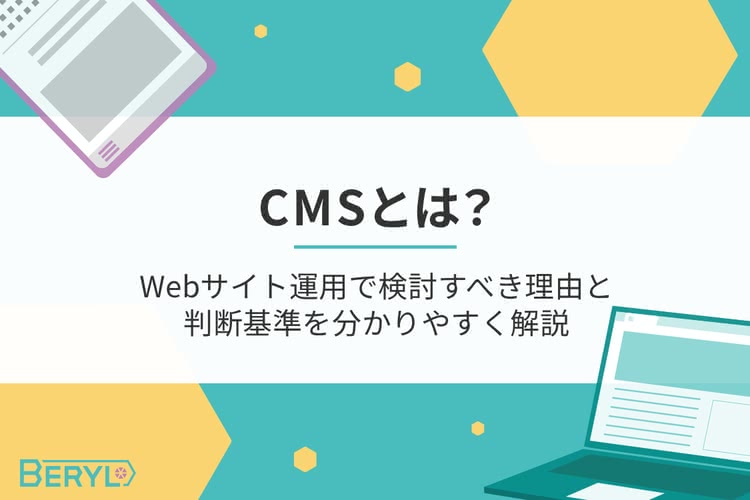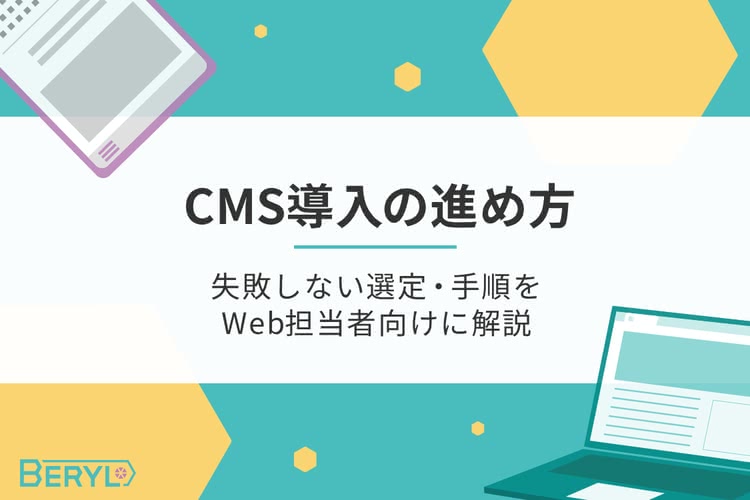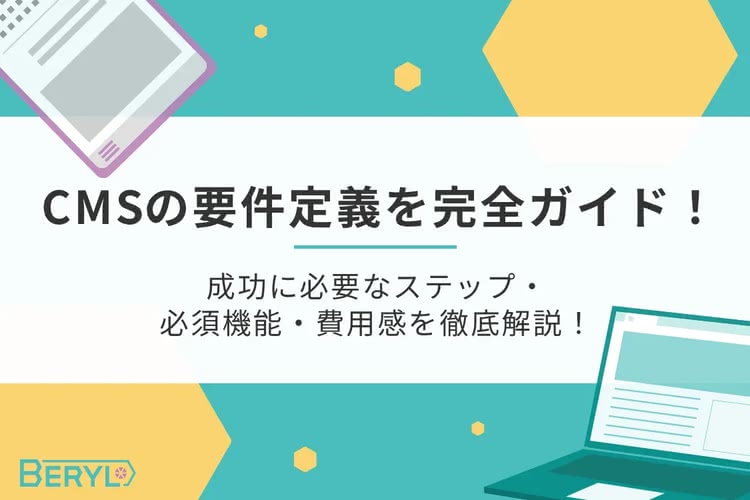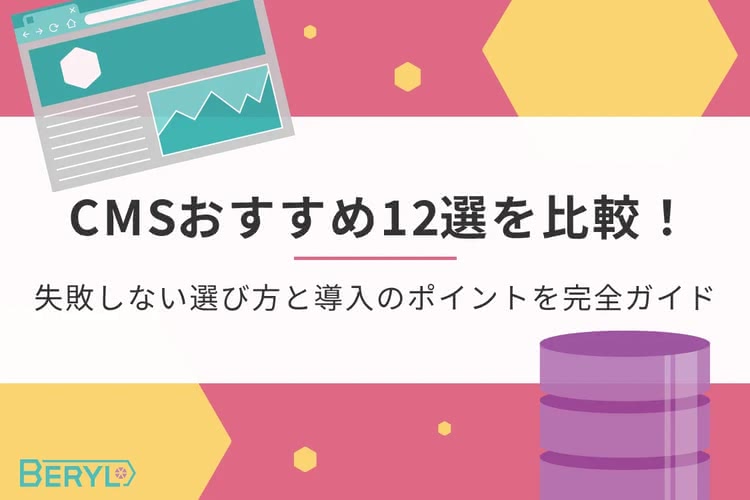CMS(コンテンツマネジメントシステム)とは何かを調べている方の多くは、単なる用語の意味ではなく、自社はCMSを導入すべきなのか、今のWebサイト運用を続けて問題ないのかといった判断材料を求めているのではないでしょうか。
この記事では、CMSの基本的な考え方を整理しながら、どのような状況でCMSが検討対象になるのかを中心に解説します。
目次
CMSとは
CMSとは、Webサイトのコンテンツを管理・更新するための仕組みです。HTMLやCSSなどの専門知識がなくても、文章や画像の追加・修正ができるよう設計されています。
重要なのは、CMSは「Webサイトを作るためのツール」ではなく、Webサイトを継続的に運用するための基盤であるという点です。更新作業を特定の担当者や外部業者に依存せず、社内で安定して情報発信を続けることを目的としています。
CMSを検討すべきタイミング
CMSが必要かどうかは、機能の多さではなく「現在の運用状況」で判断します。
次のような状態に心当たりがある場合、CMSは検討対象に入ります。
- 更新作業が特定の人に依存している
- 軽微な修正でも制作会社への依頼が必要
- 更新頻度が上がり、作業負荷が増えている
- 今後、Webサイトやコンテンツを拡張する予定がある
これらは、Webサイトの規模や重要度が一定以上になった際に起こりやすい変化です。CMSは、こうした運用上の課題を整理・分担するための仕組みとして活用されます。
CMSでできること・できないこと
CMSでできること
- 管理画面からのコンテンツ更新
- 複数人での役割分担・権限管理
- ページ構成やデザインの統一
- 更新作業の属人化防止
CMSでできないこと
- 導入するだけで運用が改善されること
- 自動的に成果が出ること
CMSはあくまで「仕組み」です。実際の運用効率は、体制やルール設計によって大きく左右されます。
CMSの主な種類
| 種類 | 説明 |
|---|---|
| オープンソースCMS | 自由度が高く、拡張性に優れる一方で、設計や運用の責任は自社側にあります。 |
| 商用CMS | サポートや安定性を重視した設計で、一定のルールに沿って運用します。 |
| ヘッドレスCMS | 表示部分と管理部分を分離し、複数の媒体にコンテンツを配信できる仕組みです。 |
どのCMSが適しているかは、「何をしたいか」「誰が運用するか」によって変わります。
CMS選定で起こりやすい誤解
CMS選定では、次のような誤解が失敗につながりやすくなります。
- 機能が多いほど良いと思ってしまう
- 有名だから安心と判断してしまう
- 現状の運用課題を整理しないまま選んでしまう
CMSは、課題に合ったものを選ばなければ負担になることもあります。選定の前に、目的と運用体制を整理することが重要です。
CMSを検討する前に整理したい視点
CMSの導入を検討する際は、次のような点を整理しておくと判断しやすくなります。
- 誰が、どの頻度で更新するのか
- どこまで社内で対応したいのか
- 将来、サイトやコンテンツはどう変わりそうか
これらを整理したうえで、具体的な導入手順や選び方を検討していく流れになります。
次に読むべき記事
CMSの基本を理解したら、次のステップとして以下の記事をご覧ください。
自社の状況に近いテーマから読むことで、判断材料を整理しやすくなります。
CMS導入の進め方・検討ステップ
CMS導入の進め方|失敗しない選定・手順をWeb担当者向けに解説
CMS選定で失敗しないための考え方
CMSの要件定義を完全ガイド!成功に必要なステップ・必須機能・費用感を徹底解説!
CMSの比較・選び方ガイド
CMSおすすめ12選を比較!失敗しない選び方と導入のポイントを完全ガイド
まとめ
- CMSはWebサイト運用を継続させるための仕組み
- 導入判断は「運用上の課題」から考える
- 比較や手順は段階的に整理することが重要
CMSの理解を起点に、次の判断へ進むための参考にしてください。
CMSやWeb運用について整理したい方へ
CMSを導入すべきかどうか、どの考え方が自社に合っているかは、記事だけでは判断しきれない場合もあります。Webサイト運用やCMSについて、現状整理や考え方の確認を目的とした相談も受け付けています。