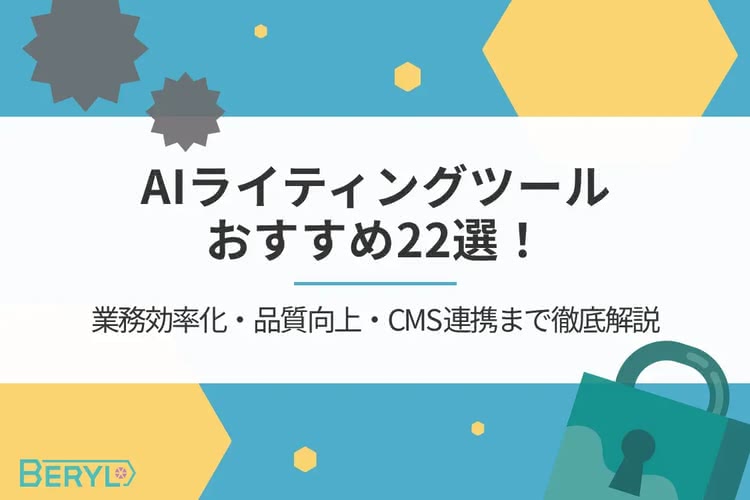AIを活用したコンテンツ制作は、いまや一部の企業だけの話ではありません。記事執筆・リライト・SEO最適化など、これまで人の手で行ってきた作業をAIが支援することで、品質とスピードを両立できる時代へ移りつつあると言えるでしょう。
ただ、「どのツールを使えば効果が出るか」「AI任せでも問題ないか」と迷われる方は少なくありません。
当記事では、AIライティングツールの仕組みからおすすめの22選、導入・運用のポイントまでをわかりやすく解説します。効率化だけでなく、コンテンツの価値を高めたいすべての方に役立つ内容です。ぜひ参考にしてください。
目次
AIライティングツールとは?仕組みとできること
ツールの基本構造から、従来の執筆手法との違い、企業が注目する理由までを整理します。
「AIが何を、どこまで担えるのか」を具体的に見ていきましょう。
1.AIライティングツールの基本構造
AIライティングツールは、自然な文章を生み出すための中核技術として「大規模言語モデル(LLM:Large Language Model)」を基盤にしています。LLMは、膨大なテキストデータを学習して文脈や語彙の関係を深く理解し、人間の思考に近い形で自然言語を生成することが可能です。
近年普及が進みつつあるChatGPT・Claude・Geminiなどの主要モデルは、与えられた指示文(プロンプト)に応じて文体・語調・構成を自在にコントロールでき、まるで専門ライターのような出力が可能です。また、多くのツール設計でアップデート機構が導入されており、利用者からのフィードバックや新しいデータを継続的に学習することで、表現力や正確性が進化し続けます。
AIライティングツールは、一般的な条件下では数秒~数分で長文を自動生成できるうえ、多言語対応や専門分野の記事作成にも適しており、企業のコンテンツ制作や情報発信における省力化に大きく貢献します。
2.従来の文章作成との違い
AIライティングツールは、従来の手作業中心のライティングを効率化する「共同執筆型」の仕組みです。AIライティングツールと従来の文章作成の特徴について、以下の表で比較してみます。
|
項目 |
従来の文章作成 | AIライティングツール |
|---|---|---|
| 作業スタイル | ライターが一から構成・執筆 | プロンプト入力で構成や本文を自動生成 |
| 作業スピード | 下調べから執筆まで時間がかかる | 数秒〜数分で初稿を生成 |
|
SEO対応 |
手動でキーワード最適化 | 自動で構成・キーワードを最適化 |
| 品質の一貫性 | 執筆者によって差が出やすい |
文体やトーンを統一しやすい |
| 編集・校正 | 人の手で確認・修正が必要 | 誤字脱字や文法を自動で確認し、読みやすさを高める |
AIライティングツールは、構成案や本文を瞬時に生成し、編集や校正の作業も自動化できるため、ライターの作業負担を大きく減らせます。ただし、AIが生成する文章は完璧ではなく、事実確認や独自性の強化には人の判断が必要です。
AIと人が協働することで、スピード・品質・信頼性を兼ね備えたコンテンツ制作が実現します。
3.AIライティングツールで変わること
AIライティングツールは、ライティング工数の削減と品質の均一化を実現できる点で、多くの企業から注目を集めています。
執筆スピードの向上
構成案や本文を自動生成することで、従来の手動執筆に比べて作業時間を大幅に短縮できます。
校正・編集負担の軽減
誤字脱字や文法の誤りをAIが自動で検出し、編集者のチェック作業を効率化します。
SEO品質の安定化
キーワード最適化や競合分析を自動で行い、一定以上のSEO品質を維持できます。
属人化の防止と継続的な運用
ライター不足やスキルのばらつきを補い、標準化された品質で記事を量産できます。
既存記事の更新・自動リライト
CMSとAIツールをAPIで連携することで、過去の記事をAIが自動で改訂し、最新情報へのアップデートを容易にします。
これらの効果により、情報発信のスピードと精度を両立し、企業全体の発信力を底上げする効果が期待できます。
AIライティングツールを選ぶ前に知っておきたい3つのポイント
AIライティングツールは「使えば成果が出る」わけではありません。導入目的やチーム体制、そして安全性を見極めることで初めて効果を最大化できます。
ここでは、失敗を防ぐための3つの視点を、順に解説します。
1.目的を明確にする(SEO/記事構成/コピー/要約)
AIライティングツールで成果を出すためには、まず目的を明確にすることが重要です。例えば、以下のようなイメージです。
- SEO記事
キーワード分析や競合比較、構成自動生成に強いツールが向いています。 - 広告コピー・SNS投稿
短文生成やテンプレート機能を備えたツールが効果的です。 - 要約・リライト
文脈理解力や自然な言い換えに優れたAIを選ぶのが効果的です。
出力形式やCMS連携の可否をあらかじめ確認し、無料トライアルで実際の生成傾向を把握することが、導入後のズレを防ぐポイントです。
2.運用体制に合わせて選ぶ(個人 or チーム or 企業)
AIライティングツールの選定では、利用する組織の規模と運用体制を踏まえることが重要です。
- 個人利用
操作がシンプルで直感的に使えるツールが最適です。 - チーム利用
テンプレート共有・承認フロー・複数アカウント管理に対応しているかを確認する必要があります。 - 企業規模での利用
ログ管理・セキュリティ機能・CMSや社内システムとの連携が欠かせません。
運用体制やスキルに応じて社内教育やマニュアル整備を行い、メンバーのAIリテラシーを底上げすることで、品質の安定化と効率化が両立できます。
3.セキュリティと著作権リスクを確認する
AIライティングツールを導入する際には、セキュリティと著作権への配慮が必須です。まず、ツールが社外サーバーへデータを送信する仕組みになっていないかを確認します。
機密情報を扱う場合は、学習データに使われないよう、設定を調整しておくと安心です。また、生成された文章に他サイトの表現が含まれていないかをチェックし、出典自動表示や参考URL挿入機能の有無を確認することも重要です。
重要な記事は必ず人の手で内容を精査し、事実誤認や不自然な表現を修正しましょう。安全性を確保する運用ルールを整えることで、長期的に安心してAIを活用できます。
AIライティングツールの主要機能まとめ(比較の基準)
各ツールの強みを見極めるには、搭載機能を理解することが欠かせません。構成生成・校正・SEO支援など、目的に応じた機能を比較することで最適な選択が可能になります。
ここでは、代表的な機能カテゴリと比較の観点を整理します。
1.代表的な機能カテゴリ
AIライティングツールには、目的や利用シーンに応じてさまざまな機能カテゴリがあります。主な分類と対応する利用者層を整理します。
| 機能カテゴリ |
主な機能 |
想定ユーザー |
|---|---|---|
| 構成生成系 |
見出し構成・目次・アウトライン作成 |
SEOライター・編集者 |
| 本文生成系 | 本文自動生成・言い回し最適化 |
ブログ担当者・広告担当 |
|
校正・リライト |
誤字脱字チェック・自然な日本語・トーン統一 |
編集・校閲チーム |
|
SEO支援 |
キーワード抽出・共起語分析・競合比較 | マーケティング担当 |
| 翻訳・要約 |
英語記事・会議記録の短縮・翻訳 |
グローバル企業・管理職 |
| CMS連携 | WordPress・ヘッドレスCMS・API連携 | Web制作・運用担当 |
構成・本文生成・SEO分析・校正・翻訳・CMSへの自動登録まで、ツールによって対応範囲は異なります。目的を明確にし、どの工程を自動化したいかを見極めることで、最も効果的なツールを選定できます。
2.比較の観点
AIライティングツールを選ぶ際は、以下の観点を意識することで失敗を防げます。
出力品質
自然で正確な文章を生成できるかが最重要です。誤情報を防ぐ技術や文脈理解力の高さを確認します。
日本語対応レベル
日本語特有の表現や文法に対応しているかをチェックします。国産ツールや日本語特化モデルは精度が高い傾向にあります。
SEO最適化機能
キーワード挿入や共起語分析、メタ情報自動生成など、SEO支援機能の充実度が成果を左右します。
チーム機能
権限設定や共有機能、承認フローが備わっていると、チームでの運用効率が高まります。
セキュリティ・プライバシー
データの送信先やアクセス権限の管理体制を確認し、社外漏えいリスクを防ぎましょう。
コストパフォーマンス
料金体系、文字数制限、無料トライアルの有無を比較し、利用頻度や目的に合ったプランを選ぶことが重要です。
このような視点を持つことで、自社のワークフローに最も適したAIライティングツールを見極められます。
AIライティングツールおすすめ22選【2025年最新版】
数多くのツールが登場するなかで、実際にどのツールが使いやすく効果的なのか分からない方は多いでしょう。
主要AIライティングツールを、料金・精度・チーム対応などの観点から一覧化しました。
短時間で自社や個人に最適な選択肢を見つけるのに役立ちます。
|
ツール名 |
特徴 |
料金 (月額) |
日本語精度 |
チーム対応 | おすすめ用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,000円 | ◎ | △ | 下書き作成 | ||
| SAKUBUN | SEO特化/共起語解析 | 2,980円 | ◎ | ○ | SEO記事 |
| RakuRin | 3,480円 | ◎ | ○ | ブログ運用 | |
| Jasper | 6,000円 | ○ | ◎ |
コピー・SNS |
|
| 文賢 | 文体統一・校正 | 1,650円 | ◎ | ◎ | 編集部運用 |
※2025年9月時点の参考価格となります。以下同。
※現時点での実用感に基づく評価となります。以下同。
下記からは、汎用型からSEO特化型、日本語特化型まで幅広く比較し、強みを明確化します。用途別に最適なツールを見つけたい方は、重点的にチェックしてみてください。
1.総合系(汎用モデルベース)
| ツール名 | 特徴 |
料金 (月額) |
日本語精度 | チーム対応 |
おすすめ用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT(OpenAI) | 汎用・高精度・安定 | 無料/3,000円(Plus) | ◎ |
○ (Team版) |
下書き作成 |
| 無料/約3,000円相当(Pro) | ◎ |
○ (Pro) |
校正・推敲 | ||
| Gemini(Google) | ○ | △ | 情報要約 | ||
| Notion AI | 要約・構成補助 | ○ | ◎ | チーム共有 | |
| Perplexity | 検索融合・根拠提示 | 無料/約2,500円相当(Pro) | ○ | △ | リサーチ |
ビジネスから個人利用まで幅広く対応できるのが、汎用型のAIライティングツールです。特徴は「一つで何でもこなせる柔軟性」と「継続的な進化」です。上記の代表的モデルは、それぞれ得意分野を持ちながらも、下書き作成・校正・要約・調査補助といった幅広い用途に活用できます。
企業利用を想定したチームプランも整備されており、共同編集やセキュリティ面でも安心です。
2.SEO特化・Webライティング向け
| ツール名 | 特徴 |
料金 (月額) |
日本語精度 | チーム対応 |
おすすめ用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| SAKUBUN(NOVEL) | ◎ | ○ | SEO記事作成 | ||
| RakuRin | 3,480円 | ◎ | ○ | ブログ運用 | |
| Catchy | 構成~執筆一括対応 | 4,800円 | ○ | ◎ | SEO・企画提案 |
| Transcope | 4,980円 | ◎ | ○ | 高精度SEO記事 | |
| EmmaTools/Keywordmap AI | 約10,000円~ | ○ | ◎ |
サイト分析・戦略設計 |
検索上位を狙う記事制作や、効率的なWebライティング運用を行いたい企業には、SEO特化型のAIライティングツールが効果的です。キーワード抽出や構成生成、競合分析などを自動で行い、ライターの作業時間の大幅な削減が見込めます。
特に、SEO知識の浅い担当者でも、テンプレートや自動構成機能を活用することで高品質な記事を作成可能です。チーム共有機能やCMS連携に対応しているツールも多く、複数人での運用にも向いています。
SEO特化型ツールは、「人が考え、AIが最適化する」形でコンテンツ制作を加速させ、メディア全体の成長を支える実践的な選択肢といえます。
3.コピー・マーケティング向け
| ツール名 | 特徴 |
料金 (月額) |
日本語精度 | チーム対応 |
おすすめ用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jasper | 広告文・LP特化 | 約6,000円 | ○ | ◎ | 広告コピー |
| SNS・短文広告向き | ○ | ○ | SNS投稿 | ||
| Writesonic | 約3,500円 | ○ | ○ | マーケ文章 | |
| HubSpot AI Writer | 要見積(CRM内機能) | ○ | ◎ | メルマガ・LP |
広告コピーやSNS投稿、メルマガ配信など、訴求力のある文章を素早く作成したい場合は、マーケティング特化型AIライティングツールが有効です。これらのツールは「短く、伝わる言葉」を生成する能力に優れており、ターゲット層に響くコピーを自動提案します。
広告・販促担当者の作業負担を減らしつつ、トーンや訴求軸のテストも効率化できます。チーム共有やCRM(顧客管理)との連携に対応したツールも多く、マーケティング全体のPDCAサイクルを高速化できる点が魅力です。
コピー・マーケティング系ツールは「スピード×訴求力」を両立させる武器です。人間の感性とAIの分析力を組み合わせることで、より効果的なマーケティング施策を実現できます。
4.日本語特化・国内開発ツール
| ツール名 | 特徴 |
料金 (月額) |
日本語精度 | チーム対応 |
おすすめ用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物語生成・自然文強み | ◎ | △ | 文章生成 | ||
| SEO特化・WordPress自動連携 | ◎ | ○ |
ブログ・Web記事 |
||
| UniCopi | SEOリサーチ・複数LLM | ◎ | ○ | SEO記事・構成 | |
| PlayAI | 登録不要・日本語特化 | 無料 | ◎ | △ | ブログ・アイデア生成 |
日本語の文脈理解や自然な語感にこだわるなら、国内開発のAIライティングツールが最も安定した選択肢です。上記のツール群は、文体・語彙・SEO指向といった日本語特有のニュアンスを的確に反映できる点が強みです。
これらのツールを活用すれば、英語圏AIでは再現しづらい日本語の自然さを維持しながら、構成案や初稿づくりを効率化できます。個人ライターから企業メディア運用まで、幅広い現場で効果を発揮できるでしょう。
5.校正・文体統一・リライト支援
| ツール名 | 特徴 |
料金 (月額) |
日本語精度 | チーム対応 |
おすすめ用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文賢 | 1,650円 | ◎ | ◎ | 編集部運用 | |
| JustRight! | 可読性・SEO考慮校正 | 約2,200円 | ◎ | ○ | 校閲・品質管理 |
| Shodo AI | リライト・表現改善特化 | 約3,000円 | ◎ | ○ |
記事リライト |
| DeepL Write | 翻訳応用・自然文補正 | 無料/有料版約2,000円 | ○ | ○ | リライト・翻訳 |
文章の品質を維持し、ブランドイメージを損なわないためには、校正や文体統一を支援するAIツールの導入が欠かせません。上記のツールは、誤字脱字の自動検出に加え、文体やトーンの一貫性をチェックし、可読性を高める提案を行うことが可能です。
企業ブログやオウンドメディア、出版業界など、多人数でコンテンツを制作する現場で特に効果を発揮します。また、AIによるリライト機能を活用すれば、既存記事の改善や再利用も効率化できます。
これらのツールを活用すれば、文章の「整える工程」を自動化しつつ、人の目による最終チェックを効率化できます。結果として、編集チーム全体の生産性を高め、媒体全体の文章品質を均一化する効果が狙えます。
無料で使えるおすすめAIライティングツール
まずはコストをかけずにAIの実力を試したい方は、無料でも体感できるツールがあります。
ここでは、無料プランやトライアルで実用レベルの出力を体験できるツールを厳選しました。有料版との違いや注意点も合わせて紹介していますので、参考にしてください。
1.無料でも実用的な代表例
無料でも実務レベルで活用できるAIライティングツールはいくつもあります。まず試す価値がある代表例は以下の通りです。
ChatGPT(無料版)
OpenAIが提供する代表的な対話型AI。約4,000文字まで生成可能で、SEO記事やブログ執筆の下書きに活用できます。
Notion AI
ノート管理ツール内で動作し、要約・リライト・アイデア出しに強みがあります。無料プランでも作業効率化に役立ちます。
Perplexity
AI検索と文章生成を組み合わせたツールで、調べながら自然な文章を作成可能です。
ELYZA Write
日本発の文章校正AI。誤字脱字チェックや文体改善に特化し、無料で試用できます。
Copy.ai
広告コピーや短文作成に強く、商用利用も可能。月10クレジット前後の無料枠で利用できます。
まずはこれらのツールで生成品質を比較し、自分の用途に最も合うものを見極めるのがおすすめです。
2.無料トライアルがある有料ツール
無料トライアル付きの有料ツールは、ビジネス利用を前提とした高機能版を体験できます。代表的なものは以下の通りです。
Catchy
SEO記事制作に特化し、7日間の無料トライアルで構成案から執筆まで自動化を体験可能です。
SAKUBUN
日本語に最適化された自然な文章生成が特徴。14日間の試用期間で広告文やブログ記事を生成できます。
Jasper
グローバルに展開する高精度AI。7日間トライアルで広告コピーから長文記事まで幅広く対応しています。
試用期間を活用し、生成品質・操作性・コストのバランスを比較すると、導入後のミスマッチを防げます。
3.無料ツールの限界と注意点
無料ツールはコスト面で魅力的ですが、以下のような制約やリスクがあります。
- 出力量やテンプレート数に上限があり、大量作成には不向き
- 商用利用が禁止されている場合があり、規約の確認が必須
- ログが保存されず、同じ文章を再生成できないケースがある
- 最新情報を取得できず、内容が古くなるリスクがある
- 誤情報や著作権侵害の可能性があるため、人によるチェックの併用が必須
無料ツールは導入の第一歩として有効ですが、長期的に安定した成果を出すには、有料プランへの移行を視野に入れることが重要です。
AIライティングツール導入のデメリット・リスク
AIライティングツールは大幅な効率化をもたらす一方で、運用にはいくつかの注意点があります。リスクを理解したうえで導入することが、成果を最大化する第一歩になります。
1.精度や事実確認に手間がかかる
AIが生成する文章には、一見正確そうでも誤情報や文脈のずれが含まれるケースが少なくありません。特に専門性の高いテーマや数値情報を扱う場合、誤ったデータがそのまま掲載されるリスクもあります。
記事の信頼性を保つためには、AIの出力をそのまま使わず、人の目によるファクトチェックと一次情報の確認を徹底することが重要です。AIをサポートツールとして位置づけ、最終的な品質を人が担保する体制を整えましょう。
2.トーンや表現の統一が難しい
AIは過去の文章データをもとに生成するため、文体がテンプレート化しやすく、ブランド固有の言葉づかいや温度感が失われる傾向があります。複数の担当者がAIを利用すると、記事ごとにトーンがばらつき、全体としての統一感が損なわれる場合もあります。
このような問題を防ぐには、スタイルガイドや語彙リストを整備し、AI出力に対して編集者がトーンを調整することが効果的です。ブランドらしさを維持するルールを定めて運用しましょう。
3.AI依存による創造性の低下
AIは整った構成や自然な文章を生成できますが、それに頼りすぎると独自の切り口や人間らしい感性が薄れ、無難で似通った内容になりがちです。SEO的に最適でも、読者に印象を残さないコンテンツになってしまうリスクがあります。
創造性を担保するには、AIが示す案はあくまで「たたき台」と捉え、人の思考や体験に基づいた意見・具体例を盛り込むことで、説得力とオリジナリティを高めることが重要です。
4.情報漏えいや法的リスクへの注意が必要
クラウド上で動作するAIツールでは、入力した内容が外部サーバーに送信・保存される場合があります。そのため、社内資料や顧客データなどを入力すると、情報漏えいのリスクや契約違反につながる恐れがあります。
特に企業での利用では、ツールの利用規約やデータ管理体制を確認し、機密情報を扱わない運用ルールを設けることは必須です。法務・セキュリティ部門とも連携し、安全な活用体制を整えることが求められます。
CMS連携で広がるAIライティングの可能性
AIで作った記事は、CMSを組み合わせることで、運用効率を一段と引き上げられます。例えば、「AIが生成したコンテンツをCMSに自動で下書き登録し、承認後に即時公開」といったフローを構築できれば、人手を介さずにコンテンツ配信を自動化し、生産性を大きく引き上げることが可能です。
ここでは、連携の仕組みと具体的な導入モデルを紹介します。
1.AIとCMSを連携させるメリット
AIとCMSを連携させる最大の利点は、コンテンツ制作から公開までの流れを自動化できる点です。AIが原稿を生成し、CMSに下書きとして登録、その後承認・公開まで一気に進めることで、担当者の作業負担を大幅に減らせます。
また、AIがメタ情報や構造化データも同時に生成するため、SEO対策を自動で最適化できます。履歴データの解析にもAIを活用でき、記事更新のタイミングや配信チャネルの選定も効率化が可能です。
結果として、制作スピードと品質を両立しながら、運用コストを削減できます。
2.AI連携に向くCMSの特徴
AIとの親和性を重視するなら、ヘッドレスCMSの導入が有効です。WordPressでもAPIを利用すれば連携可能ですが、プラグインに依存する点で拡張性に限界があります。
ヘッドレスCMSは、見た目を担う部分(フロントエンド)と管理部分(バックエンド)を分ける構造を持ち、AIが生成したデータを自在に登録・更新できます。複数サイトや多拠点運用にも強く、セキュリティ面でも優れています。
AIとの組み合わせにより、コンテンツ配信の自動化や社内システムとの統合運用も実現しやすくなります。
3.CMS×AIの導入モデルケース
AIとCMSの連携は、実際に多くの業界で成果を上げています。例えば、以下のようなモデルケースが確認されています。
- コンテンツ制作会社
構成生成から公開までの工数を半日以上短縮し、生産性を向上させています。 - BtoB企業
AIが下書きを作成し、チームがレビューする仕組みを取り入れ、記事本数を増やしています。
他にも、商品説明やLP(ランディングページ)の自動生成を進める企業も増えており、広告効果の改善にもつながっています。
このように、近年では中小企業でもCMSとAIを組み合わせることで、少人数でも高品質なコンテンツを継続的に発信できる環境が整いつつあります。
AIライティングの今後:マルチモーダル化と自律化
AIは今、文章生成の枠を超え、画像・音声・動画まで扱う新時代へ進化しています。マルチモーダル化や自律型AIの台頭により、コンテンツ制作の形が変わりつつあります。
ここでは、次世代のAI活用を見据え、企業が取るべき備えについて考えてみます。
1.マルチモーダルAIによる進化
AIは今、文章だけでなく画像・音声・動画まで扱える「マルチモーダルAI」へと進化しています。例えばChatGPT-4oやClaude 4などは、複数の情報を同時に理解し、より人に近い対話や提案を行うことが可能です。
文章生成が「読む情報」から「体験する情報」へと変化し、教育や医療、カスタマーサポート分野でも活用が拡大しています。人の五感に近い情報処理を行うことで、よりリアルで直感的なUX(ユーザー体験)を実現する段階に入っています。
2.自律型AIによる継続運用
将来的には、AIがブランドの文体や表現傾向を学習し、継続的に記事を改訂・最適化する仕組みが整う可能性があります。編集チームが定期的にチェックするだけで、AIが自動で構成提案や誤字修正を行う時代の到来です。
今後のAIは、単なるサポートではなく「自律的な編集者」として働くようになるのも夢ではありません。AIエージェントが品質監視を担えば、スピードと安定性を両立したコンテンツ制作も現実味を帯びてきます。
このままAIが進化すれば、人の判断を補いながら継続的な発信体制を支える存在となる可能性は十分にあるでしょう。
3.企業はどう備えるべきか
AIを禁止するのではなく、安全に使う仕組みを整えることが重要です。具体的には、生成物の品質を保つためのチェック体制や、情報管理のルールづくりが必要です。社内でAIの正しい使い方を共有し、利用ポリシーや教育を徹底することが信頼性を高めます。
また、AIの判断が企業ブランドに影響を与える可能性もあるため、透明性を担保した運用設計も欠かせません。AIを「リスク」ではなく「戦略資産」として活用できる企業が、次の時代の競争をリードするでしょう。
まとめ|AIライティングツールを正しく選び、運用で成果を最大化する
AIライティングツールは、単なる作業効率化のためのツールではありません。正しく選び、運用を設計することで、チーム全体の知見を活かしながら「質の高い発信」を継続できる基盤となります。
重要なのは、AIに任せる範囲と、人が関わる領域を見極めることです。適切なツールを導入し、CMSや承認フローと連携させることで、コンテンツ制作のスピードと品質は確実に向上します。
AIライティングに興味がある方は、この機会にAIを「ビジネスパートナー」として活用し、ぜひこの機会に情報発信における競争力を一段引き上げてみてください。